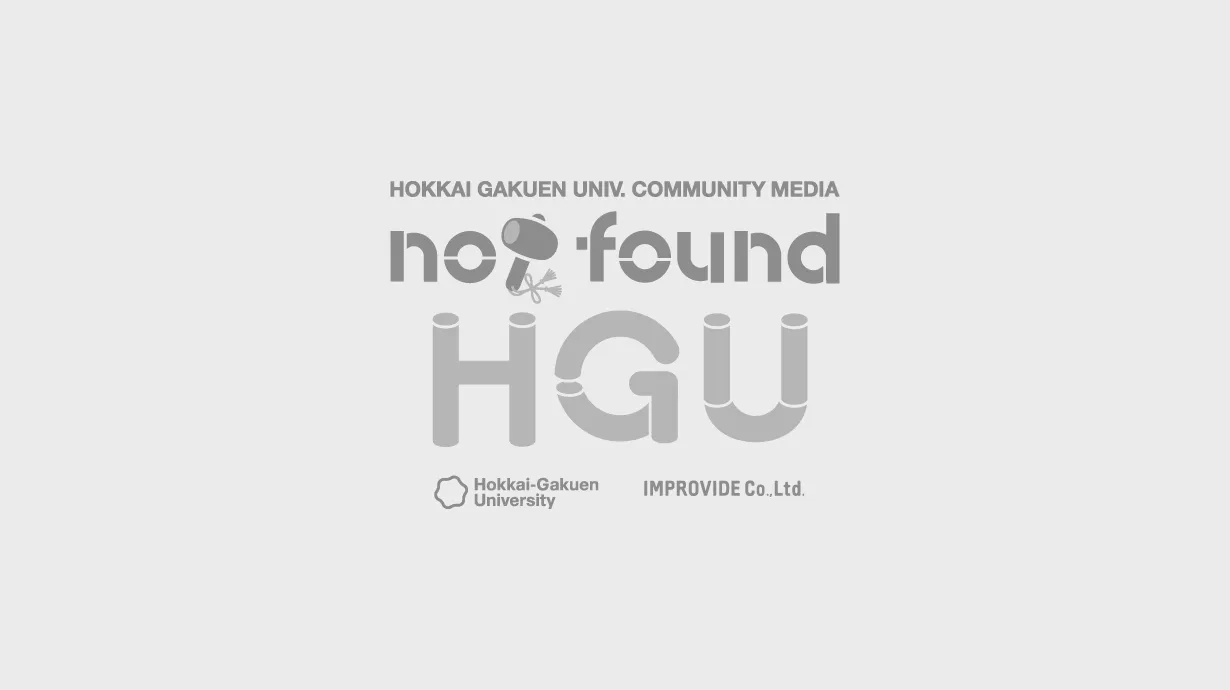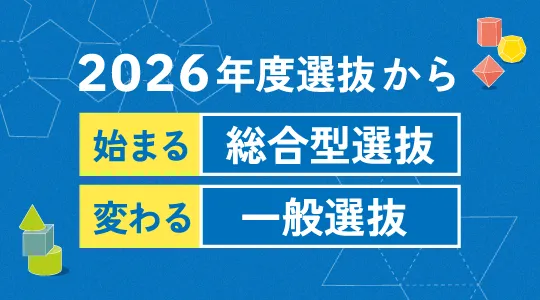裁判所の女神像が持っているのは?
——法律学を学ぶと、どんな力が身につくのでしょうか?
私は法学部を目指す高校生に「リーガルマインドが身につく」という話をよくします。リーガルマインドは、日本語では法的精神や法的思考力と訳され、裁判所の姿勢ともいえます。
皆さんは、裁判所にある女神像をご存じですか? 女神像は一方の手に剣を持っています。これは正義の象徴。「悪には屈しません」という姿勢の表れです。もう一方の手には天秤。これは公平さ、公正さを表します。そして、女神像は目隠しをしています。なぜでしょうか?
——小さな罪には目をつぶる? ……そんなはずはないですね。
ハハハ、違います。これは、先入観にとらわれず判断する姿勢を表しています。「この被告人はコワモテだから罪を犯したに違いない」と決めつけてしまえば、本当は罪に問われない人が有罪になる——これが冤罪(えんざい)です。裁判所は、こうした冤罪を絶対に避けなければなりません。
先入観を排し、双方の言い分を丁寧に聞き、問題の本質を見極めて判断する。この姿勢が、リーガルマインドの根本にあります。

——裁判官や弁護士に求められる姿勢ですね。
はい。ただし、これは法曹界だけでなく、あらゆる職業・組織で求められる力です。本質を見極め、論理的に説明できる力、リーガルマインドは一朝一夕では身につきませんが、裁判所の法的判断やそれに関する議論等を学び続けることで、自然と培われていきます。
海外進出に失敗した!経営責任は問える?
——草間先生は商法、特に会社法が専門だそうですね。授業ではどんなことを?
私は、コーポレート・ガバナンス(企業統治)を研究しています。会社の経営に関する意思決定を行う取締役には「善管注意義務」があります。噛み砕いていうと、取締役は「会社の利益のために注意を用いて職務を行わなければならない」という義務です。適用場面は、大きく二つ。一つは経営判断、もう一つは不祥事防止のための監視です。ここでは、経営判断の例を紹介します。
例えば、回転寿司チェーンを営む草間株式会社の取締役である皆さんが、2年後にA国に進出するかどうかを検討しているとします。A国では魚をたくさん食べますが、生で食べる習慣はありません。さて、皆さんなら出店しますか?

——私は反対です。失敗しそうだからです。
なるほど。講義やゼミでも意見が分かれます。「前例がないなら調査した上で挑戦するべき」という積極派の人もいます。議論の結果、賛成多数でA国への出店が決定しました。しかし大失敗に終わり、何億円という損失が出たとします。
——ほら、やっぱり!賛成派は責任を問われますか?
ここで争点になるのが善管注意義務です。もし裁判所が「生食文化のない国に進出するなんて、きちんと注意を用いて判断したとは考えられない」と、結果論的に善管注意義務違反を認めるとします。そうなると、どうでしょう? 失敗=違反となれば、経営者は萎縮し、チャレンジしなくなるはずです。それを防ぐために、取締役が行った経営上の決定をめぐり訴訟が提起されたら、「その決定内容とプロセスが著しく不合理でなければ、その取締役は善管注意義務違反に基づく損害賠償責任を負わされない」という経営判断原則が適用されます。
例えば、事前調査で「生魚は食べないが炙りは好む」と分かり、炙り寿司メニューを開発して出店したなら、きちんとリサーチした上での判断ということになりますから、善管注意義務違反に問われない可能性が出てきます。
商法の授業やゼミでは、こうした設例を出し、グループで議論・発表を行います。

——法律学科は法曹界に進む人以外にも役に立つ学びがありますね。最後に、大学進学を考える皆さんへのメッセージをお願いします。
大学での4年間は、社会に出るための準備期間です。将来、仕事をする中で、さまざまな人と関わりながら協力して物事を進める必要があります。そのためにも、大学生活ではゼミや課外活動を通じて多くの人と交流し、コミュニケーション力を高めてください。
社会では、意見の対立や困難な課題に直面することが少なくありません。法律学を学んでおけば、物事を冷静に分析し、解決策を導く力が大きな強みになります。
ぜひ、大学で法律を学び、問題解決力を養ってください。皆さんと一緒に学べる日を、心から楽しみにしています。

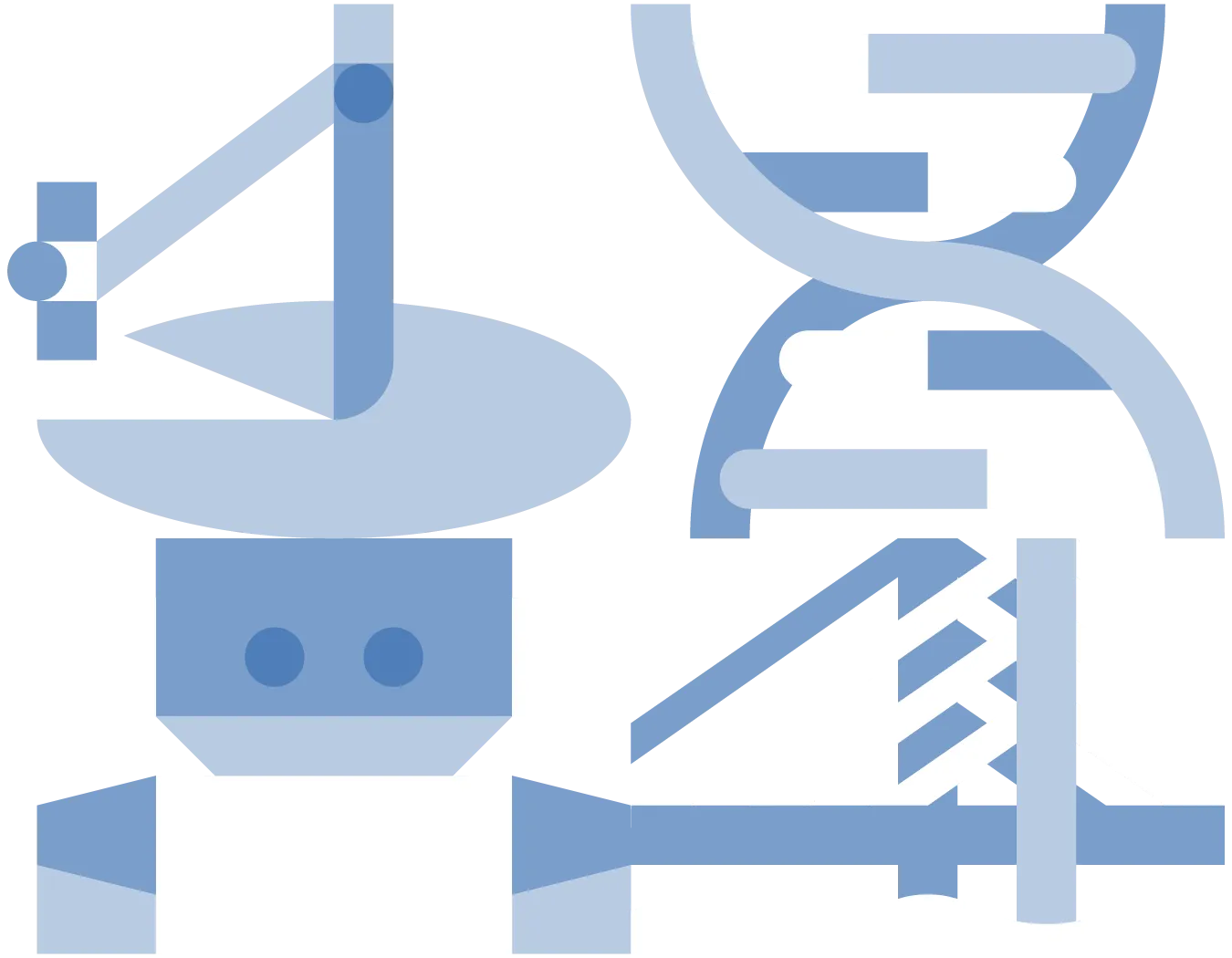

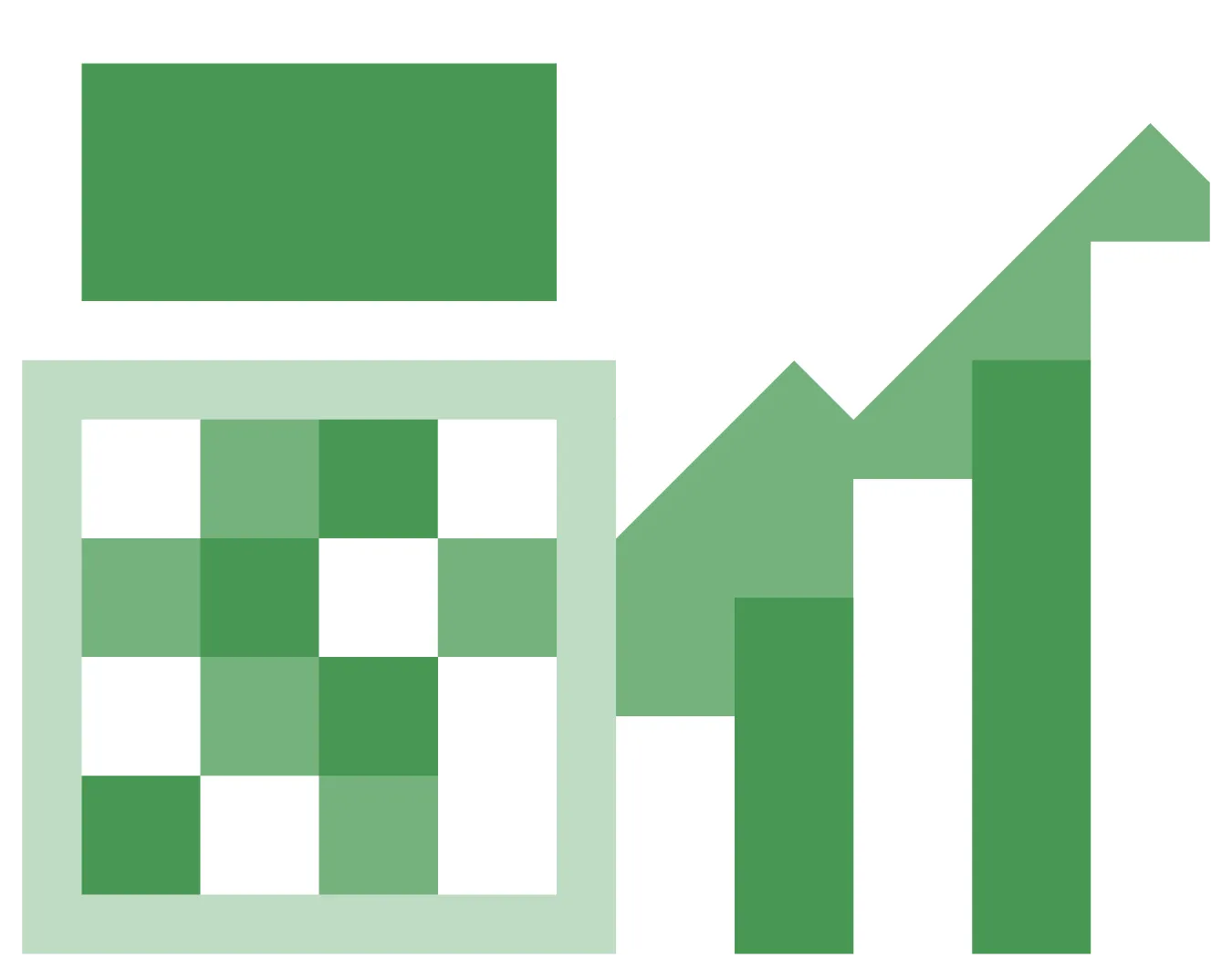
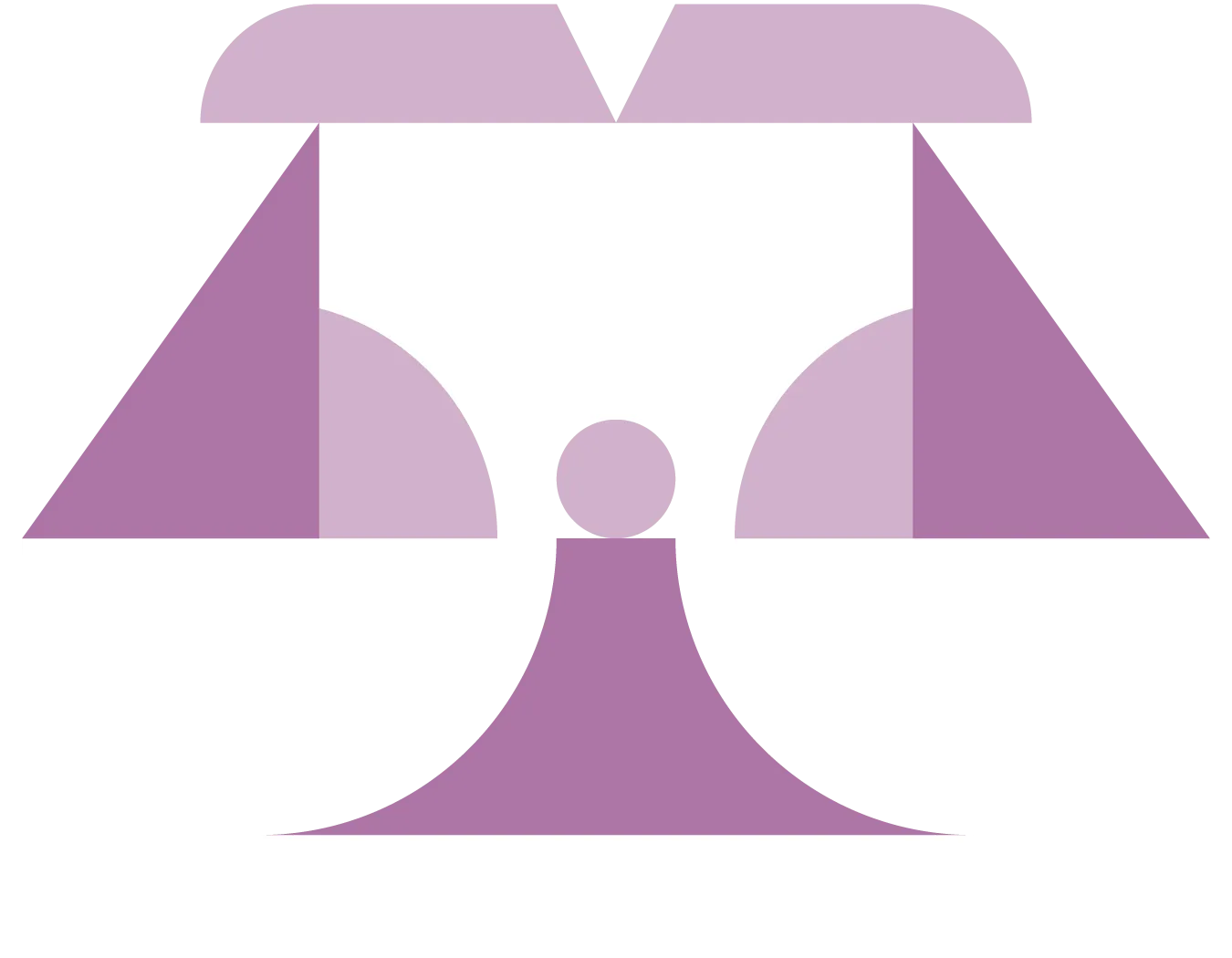

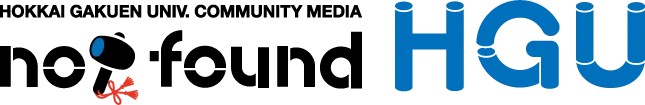





.png)